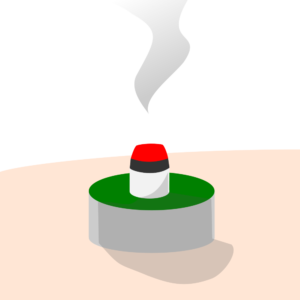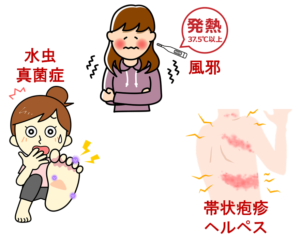免疫力が弱い人の特徴がわかる、東洋医学での防衛力についの続きです。
風邪をひいたかな?というときに役立つ対処法を前の記事に載せています。まだお読みでない方はどうぞお読みください。
免疫力=防衛反応
免疫力を東洋医学では「氣」が司ります。「氣」のなかでも「衛氣(えき)」といい、肌表面(厳密には体表肌に接していない部分)にある体表面のバリアのようなものです。このバリアでウイルスなどの外敵から体を守ってくれる働きをしています。
衛気について
これから、免疫力のことを「衛氣」と言い換えていきます。
「衛氣」 は体内の経脈に入ることは出来ずに経脈外を循行しています。 「衛氣(えき)」 は一種の比較的なめらかな、またすばやい水穀(飲食物)の化した気で、特定の路線をめぐるものです。皮部を充たし、腠理(そうり)を肥やし、開闔(かいごう)を司る。発汗の調節をします。わかりやすく解釈すると体表張り巡らせたバリアのイメージです。皮膚や鼻・気管支などの粘膜細胞強化して免疫力を整え、外敵(外邪)に反応する「気」で体表を守るように全身を回っています。
次からは、衛氣不足の具体的な症状、不足する要因、その他の衛気の働きについて解説してまいります。
弱くなりやすい時期は?
外の気温が下がるとき、冷たい風が吹くときなどは一般的に風邪をひきやすいと認識されています。それに加えて湿度が下がる=乾燥する時期の注意が必要です。
乾燥することによって、肌の潤いがなくなり、硬くなったり、白い粉ふいてパラパラはがれてくることはありませんか。この状態ではバリア機能が正常に働かないため免疫力が弱ります。
衛氣が強ければ免疫力が働くので外邪は入ってきません。

免疫力=衛氣が弱いと外邪がそこから入り込んできます。

その他の衛氣不足の症状
衛氣が不足している状態を「衛氣虚」と言い、外的刺激の影響を受けやすくなります。
具体的には、
- 風邪をひきやすい
- 疲れやすい
- 呼吸器系の異常
- 多汗
- 季節の変わり目や気温変化に体調を崩しやすい
- 体の痛み
と意外にたくさんの症状が起こりえます。
上記は、自律神経の乱れ・更年期障害で起こる症状に多く現われるものでいかに衛氣が重要な働きをしているかがわかります。
衛氣不足の要因
不規則な生活や睡眠不足、過労、食生活の乱れ、運動不足、生活環境、加齢、薄着などがあげられます。この中には、生活習慣や日々の心構え、意識の仕方で対処できるものが含まれますね。
ただし、上記に当てはまらない懸念事項があります。
- 胃腸の働きが弱い
- 病後で体力が落ちている
- 高齢の方などは、食物から栄養を吸収して体に巡らす力が落ちてしまい、衛気を作り出せなくなっていますので注意が必要です。
また、花粉症などアレルギー疾患がある場合、粘膜の反応が通常と異なります。
衛氣が弱い皮フの例
病邪の人体への侵襲は、必ず皮部からはじまるといい、
皮部は経絡が外邪を防ぐ障壁であると言えます。
施術時に体の観察をしていると、
ある一部分に産毛が濃く生えていることがあります。
人によって部位は様々ですが皮毛の毛を意識するとこれは衛氣がその部分を守れないために産毛で覆っている現れと診ています。
(肌に赤い斑点などあることも)

*だいたいこういう背中の人は、いつも肩背中(肩甲骨の間位)が凝っています。とおっしゃいます。こりや痛み等も衛氣不足で起こることがあります
特に日頃から首から肩、背中が凝り固まってしまっていると気がうっ滞していて、衛気も十分に働けていません。常に冷えていることもあるので、ゾクゾクした感じがなく気づかないうちに外邪が入り込んでしまいます。
免疫力が弱い?特徴の人に注意してもらいたいこと
乾いたタオルなどで皮膚を摩擦して皮膚自体を強くしましょう。いわゆる乾風摩擦です。ほかに 日光浴に浴びてください。日光浴は洋服の上からでかまいません。できれば夏に海水浴をするとよいですし、裸足で砂浜を歩くだけでも良いですね。
アーシングとも言われますが、現代社会において免疫力を低下に繋がる静電気の除外の術になると思います。
衛気にはほかの働きもあります
衛気は一日一夜に体を50周巡ると考えられています。
昼間は陽を25周、夜間は陰を25周めぐる割合です。
*当室では鍼を刺して置いておく時間をここから算定して採用しています。

日が暮れて衛気が陰をめぐると睡眠に入ると考えられています。
陰に入れないと常に陽に留まるので、陰陽の偏盛が生じるとともに、陰の気が虚して安眠できなくなると考えるのです。現代人の不眠の傾向のひとつといえます。
それぞれの体の状態を見極めたうえで、衛気による場合施術で調整していきます。

衛気は目に見えないのでイメージしにくいですが、いろいろな働きがあり奥が深いのです。
昼夜逆転を現代に当てはまるとすれば、「自律神経失調証」
テレワークや受験勉強など、根を詰めすぎたり定期的な運動週間がなくなることは「自律神経」を乱して、イライラの原因になります。
関係ないと思っているその症状、自律神経の乱れかもしれません。
そして、東洋医学は「氣」の医学と言われ、その他たくさん種類の「氣」がありますが、どれも生活習慣に根付いて不足(虚)します。
まだ不足していなくても「夜更かし」「食生活の乱れ」など意識して見直しながら健康維持を心がけていきましょう。
当院では、気の流れを整え巡らせる方針で行っています。表層の氣=衛氣と深部の氣=営氣です。
衛氣が乱れている場合、整えると体の動きが変り痛みが取れることがあります。
今まで取れにくかった痛みや動きの悪さは、衛氣虚かもしれません。(個人差があり鑑別が必要です)